| 赤沢自然休養林 |
古くから木曾街道の宿場町として栄えてきた上松は、今なお檜に代表される、木曾木材の産地として
その美林を守りつづけ、赤沢自然休養林は、森林浴発祥の地として、忘れかけた素顔の自然と対話できる
そんな、スポットです。
|
|
 |
赤沢へのアプローチは、寝覚めの床をすぎ19号を
旧道へおり、木曽川を渡るところから始まります。
支流の小川をさかのぼること15分。
檜の集荷場発見。
かつては、いかだに組んで木曽川を下った(中乗りさん)
木材も、今ではクレーンとフォークリフトで
トラックに積んで出荷するんでしょうね・・・
昔の姿を見てみたい気がします。 |
 |
 |
 |
いくつも小さな橋をわたり、右に左に渓谷は深くなって
いきます。
新緑の若葉を水面に写して、水はエメラルド・・・
|
|
 |
 |
 |
やがて休養林駐車場に到着。
目の覚めるようなあざやかなピンクのミツバツツジが
迎えてくれました。
奥には「森林浴発祥の地」の石碑。
さらには、森林鉄道の記念碑
昭和50年まで、木曾の山中で木材運搬用として
活躍し、林業の近代化の象徴ともいうべき森林鉄道の
森のなかで脈々とつづられてきたであろう、さまざまな
物語を感じさせます。
|
 |
 |
昔、木材運搬に使われていた森林鉄道が復活。
小さなディーゼル機関車に引かれた客車が、
赤沢美林内を、運行しています。
走行距離は往復2.2Km。
手押しのトロッコからはじまり、蒸気機関車の導入、
そしてディーゼル機関車の出現まで、その発展と
はたした役割は、日本の林業を支えるもの・・・
そんな面影を感じさせてくれる駅舎です。
|
 |
 |
ボールドウィン号
アメリカ製の蒸気機関車で大正4年から昭和35年まで
約42万キロを走りぬいた実際の車両が古き時代を
偲ばせながら展示されています。 |
列車は、この時期30分毎に運行されています。
(土・日・祝)。季節によって異なるようですので要注意!
大人700円也。
右の写真のように木製の切符です。
いかにも、森林鉄道らしく、檜の良い香りがします。 |
 |
 |
 |
列車は出発。
鉄道記念館駅を後にします。
ゆっくり、ゆっくり汽笛をならしながら・・・
ゴトゴト、ゴトゴト ポッポ〜・・・
気持ちよい振動が足元からつたわります。
途中、ハイカーとふれあいながら、白樺、檜、朴の木
等の木々をくぐり抜け、清流に沿って約10分で
終点丸山渡へ到着。 |
 |
 |
 |
木曾五木を覚えました。
パンフレットよりご紹介します。
|
 |
 |
丸山渡からふれあいの道を少しおります。
このコースは車いすでも楽に楽しめるよう配慮され
段差もなく前線をレンガと木道で整備されています。
石楠花が咲いていました。
|
 |
最初の橋は、呑雲渕(どんどんふち)と読みます。
渕とは、水の流れが深くよどんでいる所をいいます。
一枚板の岩の上を勢いよくどんどんとリズミカルに
音を発し流れ落ちる様子と、雲が渕に映えて美しい
ことからこの字があてられた、とのことです。
|
 |
 |
 |
 |
駒鳥コースへ足を踏み入れてみました。
このコースは、先ほどとは打って変わって
木の根が網状に、からみあった道。
いかにも”森林の中を歩いている”そんな
気持ちが味わえるコースです。
丸葉橋で再び合流。
線路も見えます。 |
 |
ポッポ〜
警笛と共に、折り返しの列車がかえってきます。 |
 |
 |
 |
 |
水は相変わらず透明
あちこちに渕と早瀬をつくっています。
みずばしょうの葉は、30Cmにもなり、
朴の葉はまだまだ小さく芽生えたばかり・・
 |
 |
 |
アスナロ橋をへて中立橋まもなく終点です。
夏休みにはこのあたりが、子供たちの流水プールに
なります。 |
 |
 |
鉄道記念館には、当時の道具や写真、資料が展示され
下の森林資料館には、伐採の道具類、木製の楽器
生息する動物のはく製などが、展示されています。
|
 |
 |
 |
森林浴は、疲れた頭のリフレッシュに最高!
あたり一面、緑一色。
植物が発散する新鮮な酸素を、おもいっきり吸い込み、
聞こえるのは小川のせせらぎと小鳥のさえずり、そして木立を抜ける風の音。
秋の紅葉も素晴らしいとのこと
春・秋と2回おとずれたいスポットです。 |
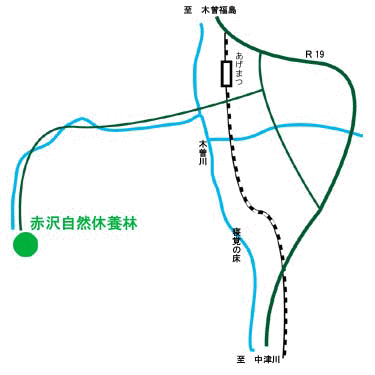 |
 |
 |
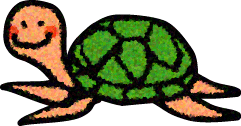 |